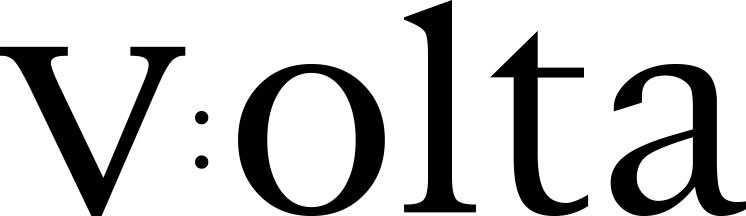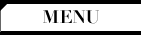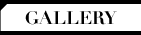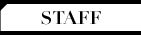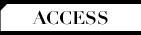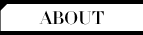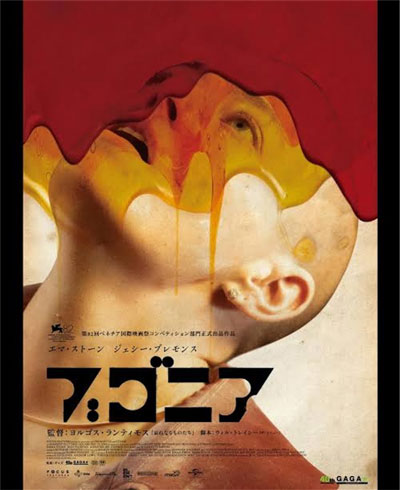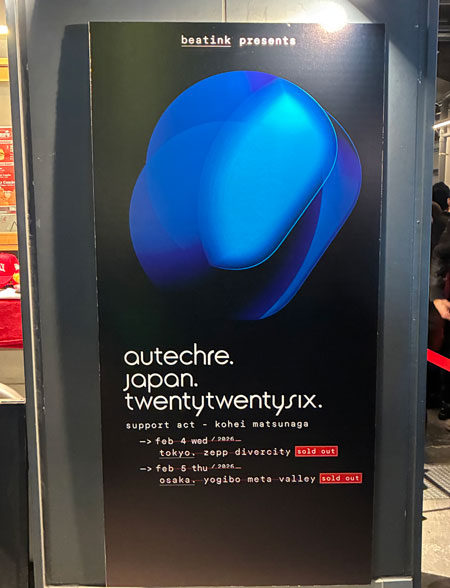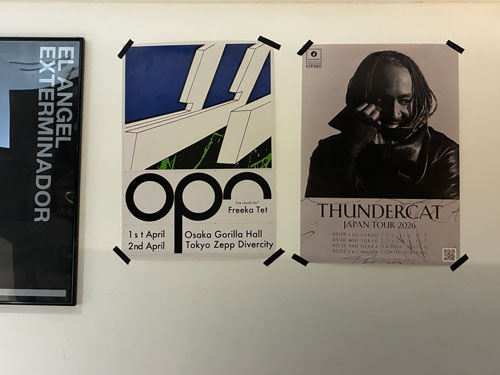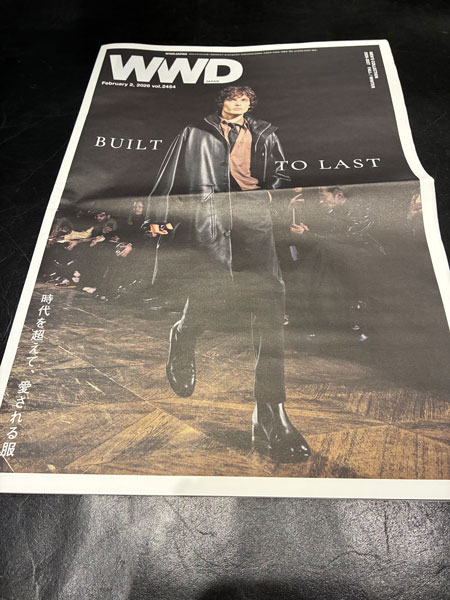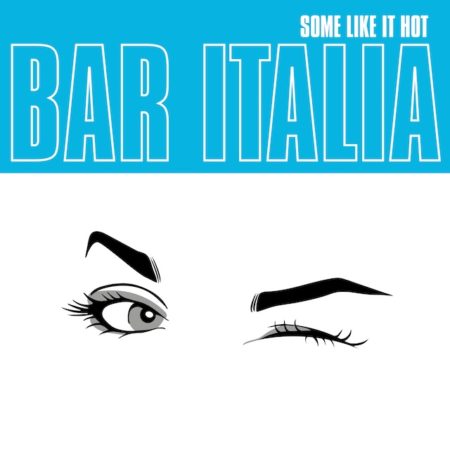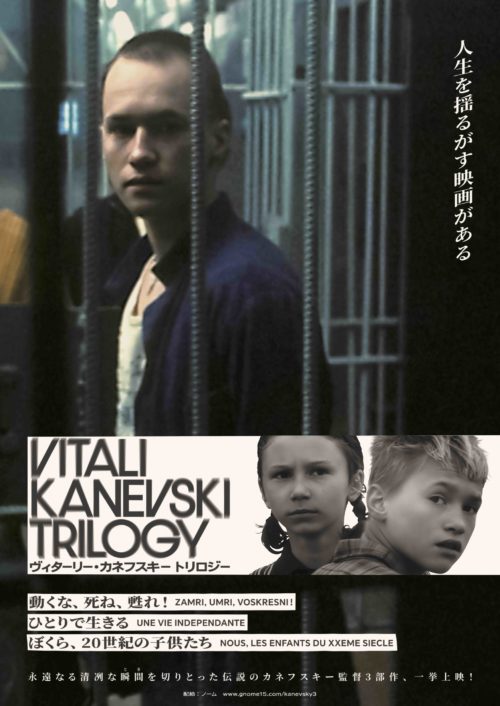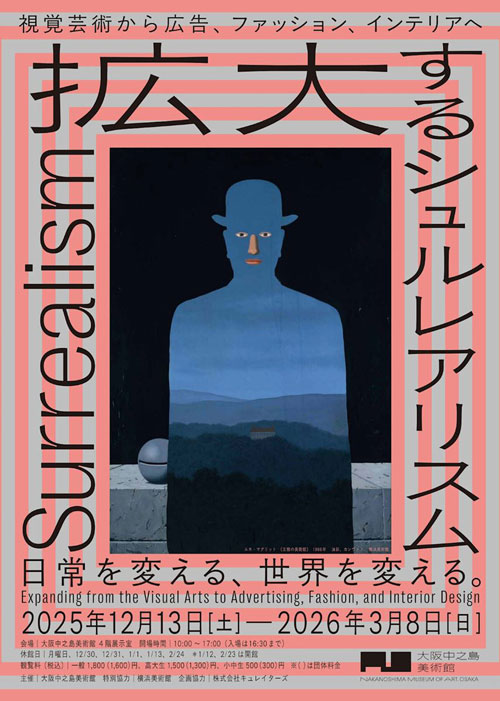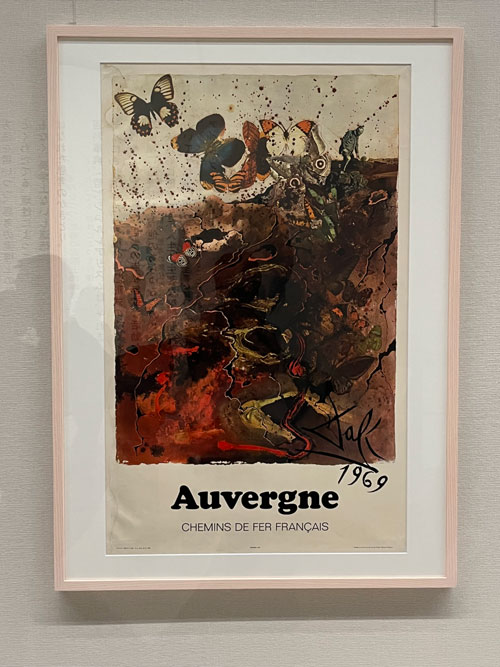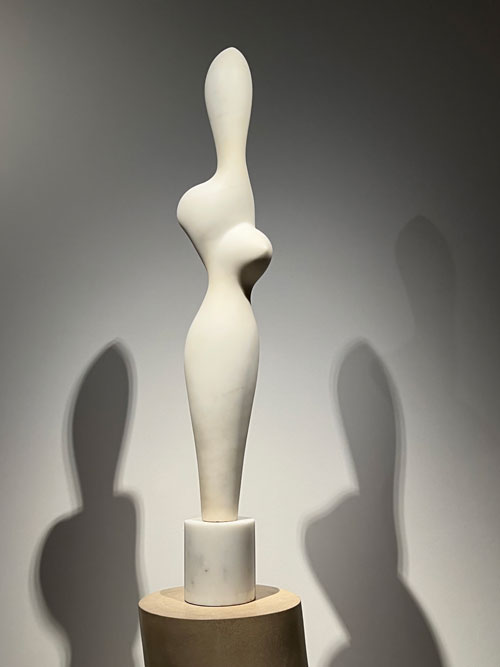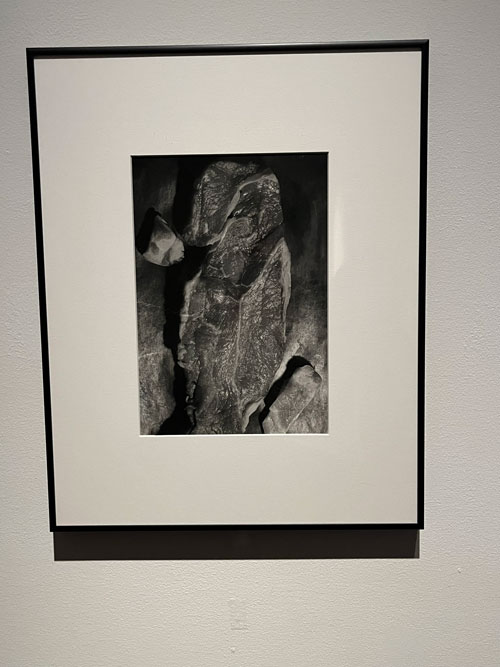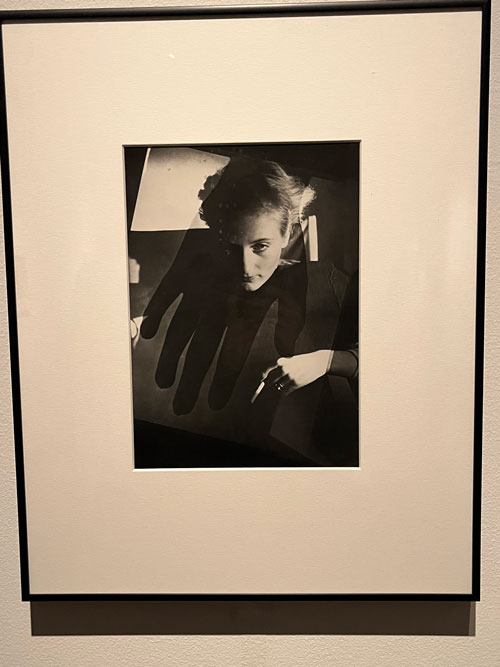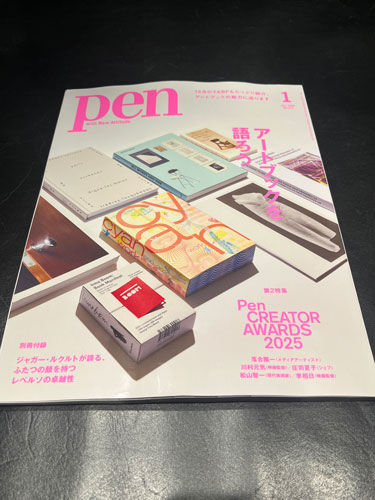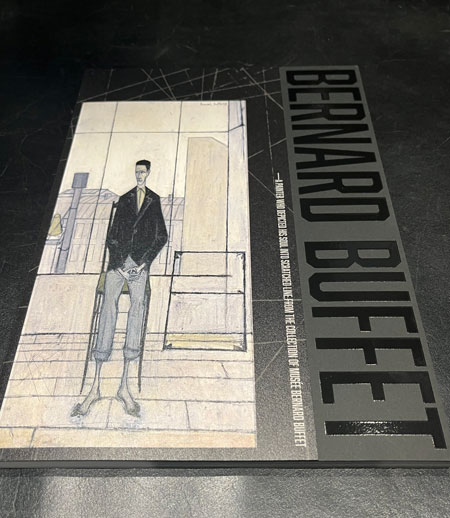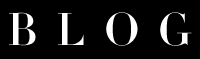美容業界専門誌の『美容の経営プラン』さんからコラムをご依頼いただき、寄稿させていただいたものを掲載していただきました。

“カネ”、“モノ”、“ヒト” の中から一つテーマを選んで書いてほしいということだったので、「今、社会に実装していっているAIやロボットがどのように美容業界に取り入れられていくのか」ということについて自分が考えたりしていることを少し書かせていただいたのですが、コラムの文字数ではどうしても簡潔にまとめる必要があったので、こちらでは文字数気にすることなく書かせていただこうと思います。
ご興味のある方は、読んでみてください。
.
現在、AIやロボットが社会に広がっていく中で、今後無くなっていくと思われる職業ランキングみたいなものをご覧になったことがある方もいらっしゃるかと思います。
それらに代替されていくと思われている職業の上位は、一般事務職やスーパーのレジ打ち, 倉庫内作業,薬剤師,タクシードライバーなどです。
アメリカのビッグテックと呼ばれるような企業が最近従業員を大量解雇したニュースを頻繁に目にするようになってきましたが、これらのまさに人の代わりにAIやクラウドサービスを販売したいと思っている企業はそういう波が社会に広がっていけば自分達の企業の利益が上がるので、率先して大々的に行うことで注目度を上げたいという意図もありそうです。
では、美容師はどうかというと、今のところ無くならないであろう職業だとされていますが、それだって10年後はどうなっているかわからないですし、現在美容師が行なっている業務のうち、いくつかの業務はAIやロボットが代替するようにはなっていくと思っています。
このテーマのコラムを書こうと思ったきっかけは、今年の始めにオプティマスというヒト型ロボットを作っているテスラ社のCEO,イーロン・マスク自身の髪を自社のロボットがカットしている動画がXに流れてきたのを見たことにあります。
この時は、もうロボットの進化はここまで来ているのかと思ったのですが、少し調べてみるとこの動画もAIによって作られたフェイクだということがわかりました。
今SNSなどに流れているフェイク情報やフィルターバブルといったものも、人の思考や行動に影響を与え始めてて怖いなと感じているのですが、ロボットが人の髪の毛をカットする動画は現時点ではフェイクでも、いずれフェイクじゃなくなる時代が来るのだろうなと思わせられるものでした。
美容師という職業は、就職していきなりお客様を担当できるわけではなくて、最初はアシスタントとして先輩スタイリストの業務を補助しながら技術を身につけていき、さらに業務時間以外でも個人で練習したり、カットモデルなどをこなしていくことで一定の技術力を身につけた上でスタイリストとしてデビューします。
顧客を多く持った美容師は、自分ひとりでは担当するお客様をこなせないので、アシスタントにシャンプーやカラーなどの業務を補助してもらうことで複数の客を掛け持し、特に忙しいスタイリストともなるとカットと仕上げ以外はほぼアシスタントが担当するという仕事の仕方でなんとか回してるという人も中にはいます。
でも、そういう人は全体的には一握りで、今の業界の主流はひとりの美容師が自分の顧客を最後までひとりで担当するというスタイルだと思います。
これは美容師数の増加によって顧客を多く抱える美容師が減っているということもありますが、業界の人手不足でアシスタントが必要でも採用できなかったり、人件費や材料費の高騰でスタッフひとりひとりの生産性を上げなければならないからアシスタントを置くことができない美容室も増えてきているのだと思います。
最初は、そういった人手不足で本当は人員が欲しくても採用できないというところに、ロボットは入っていくと思います。
美容業界には、すでにオートシャンプーという自動でシャンプーをしてくれる機器がありますが、現状人の手がシャンプーしてくれた方が気持ちがいいから一部でしか浸透していません。
ですが、人と同じくらい、さらに人よりも気持ちがいいシャンプーができるものが開発されたら、美容室は喜んでこれを採用すると思います。
ヘアカラーのメニューでも、ホイルを使うようなデザインカラーはいきなり難しくても、技術が比較的簡単な白髪染めをしてくれるようなロボットならテクノロジーとロボティクスに強い企業が組んで本気で取り組めば近いうちに実用的なものを作れる気がしますし、そうなれば「白髪は染まればそれでいい」というくらいの人なら現在より安い値段で定期的なリタッチができる世の中になっていくと思います。
今でも白髪染めなどのカラー専門でやってるチェーン店みたいなところは増えています。
とにかく安く白髪を染めてくれたらそれでいい、という方にとっては大変便利なサービスだと思います。
本当はそうじゃなくても、日々の暮らしが厳しくなれば、生活水準を下げなければならないという理由でそういったお店を選択する人もいらっしゃると思います。
現代の日本においては、そういう方のほうが割合が多いのではないでしょうか?
単なる白髪染めのリタッチであっても、仕上がりの繊細な色の違いや頭皮や髪の毛への負担というものにこだわりのある人にはそこでは満足できないと思いますし、自分も全ての技術において自分なりのこだわりを追求したいと思って美容師をしているので、そういったこだわりを持った方や違いを理解してくださる方に選んでいただけるように日々精進している次第であります。
僕は自分の顧客さんに使うカラー剤は、基本的に自分が調合します。
それは、その人に合った調合を匙加減の微妙な違いにまで工夫して作りたいと考えるからです。
いつも同じ色を希望される方でも、季節やその時々の感覚や気分によって微妙に調合を変えることもあります。
塗布する作業は別のスタッフに任せたとしても、カラーの色味には自分のクリエイティヴィティみたいなものも少し入れたいと思っています。
当店には、その細やかな違いを理解してくださりそこに特別な価値を見出してくださっているから顧客となって通ってくださっている(もしくは違いはそこまでよくわからないけどそういう点に関して頑張っていそうだから応援の意味も込めて通ってくださってる)、という方の割合が比較的多いほうだと思います。
将来、美容師の仕事のうちロボットに代替されないところは、そういう作り手側の細やかな工夫や考えの詰まった人間ならではの技術の部分であってほしいなと思う今日この頃です。

日本はこれからさらに少子高齢化の時代を迎え、働き手の数も減少していきます。
現在においても毎年のように税金が高くなり一人ひとりの負担が大きくなっている原因のひとつは、働き手の母数が日本人の総人口の減少以上の割合で少なくなっているからです。
日本は社会構造においてこれから大きな改革をしていかないと、この先今よりも不便で厳しくなっていく現実が待ち構えています。
人間とAIやロボティクスがうまく共存することで、正念場を迎えつつある日本の将来に明るい光が差すことを信じて願っています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!